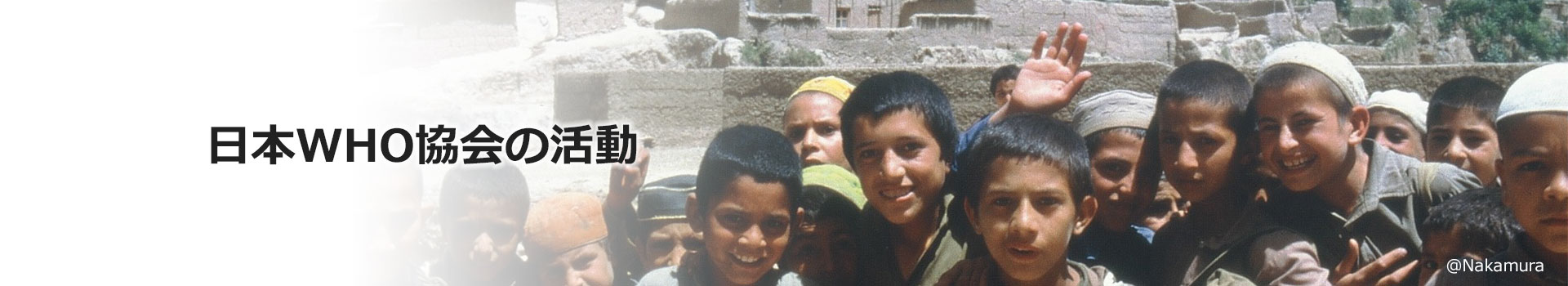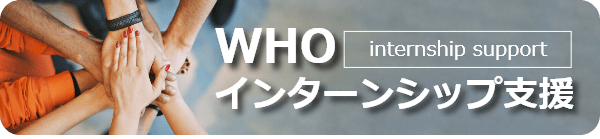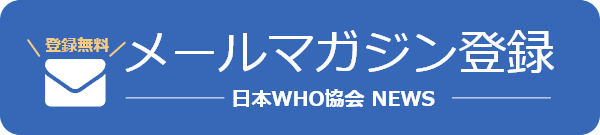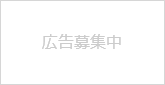世界的に、マレーシアやタイや台湾などでもおちついたはずの新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の再燃が心配です。世界中のどこかでCOVID-19の火種があるかぎり、新型コロナ対策が終息することはありません。まさに、世界各国との国際協力を強化して、グローバルな協働を積極的にすすめていくときだと痛感しています。
さて、公益社団法人日本WHO協会の関西グローバルヘルス(KGH)の集いの「オンラインセミナー第3弾・COVID‐19からの学びは国境を越えて」が5月12日に開催されました。今回のテーマは、「保健ボランティア:なぜ、日本には活躍の場がないのか?」でした。
タンザニアの保健ボランティアについて小松法子さん(創価大学看護学部)が報告し、シェア=国際保健協力市民の会の仲佐保さんからはエボラウイルス熱のコンゴ民主共和国の実情をふまえ、保健ボランティアの役割を話していただきました。また、KGHの運営委員でもある佐伯壮一朗さんが COVID-19で自粛を強制された日本の医学生の姿を報告する一方、英国のUniversity College London医学部の医学生である島戸麻彩子さんが、学生ボランティアとしてCOVID-19の現場で活動する医学生の姿とそれを支援する大学教員の姿勢を報告してくれました。医療は文化です。同じCOVID-19という新興感染症が席巻したなかで、英国と日本で医学教育の対応がこれほど異なるのかという点でも驚きでした。
COVID-19で外出制限が厳しくなり、医療者がコミュニティに入っていけないなか、世界の多くの国では保健ボランティアが活躍しました。赤十字のボランティアが活躍したイタリア、医学生が診療の手伝いをした英国、平時から活動していた保健ボランティアが地域に密着し病院や行政と住民の間をつないだ多くの低中所得国。
なぜ、日本では保健ボランティアが活躍する余地がなかったのでしょうか? 医療崩壊の寸前で人手が不足している状況にもかかわらず、平時のしきたりと論理が優先します。この硬直した社会構造はジリアン・テットが『サイロ・エフェクト』で指摘した高度専門化社会の罠を彷彿とさせます。保健ボランティアの課題を真摯に追求することで、変わらなければならない日本社会の姿が見えてきたという印象をもちました。
今後も、保健ボランティアの課題について考えていきたいと思います。
公益社団法人 日本WHO協会
理事長 中村安秀